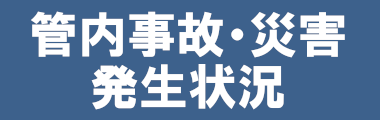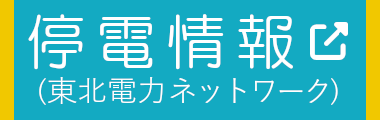免状交付申請に必要な関係学科の取得単位は別表第1、別表第2のとおりです。
表中「授業科目」において、◎科目は必修科目ですので、取得していない場合は、単位不足となります。
| 科目区分 | 授業科目 | 大学等 | 短大等 | 高専等 | 高校等 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1号に関するもの a 電気・電子工学等の基礎 |
○電気磁気学 ○電気回路理論 ○電気計測 ○電子回路理論 ○電子工学 ○システム基礎論 ○電気電子物性 |
17 | 12 | 11 | 6 |
| b 電気基礎実験 | ○電気基礎実験 | [2] | [2] | [4] | [4] |
| 第2号に関するもの a 発電、変電、送電、配電等 |
◎発電工学又は発電用原動機に関するもの ◎変電工学 ◎送電工学 ◎配電工学(屋内配線を含む) ○高電圧工学 ○システム工学 |
7 | 5 | 5 | 2 |
| b 電気応用実験、電気実習 | ○電気応用実験 ○電気実習 | [1] | [1] | [3] | [2] |
| c 電気製図 | ○電気製図 | {1} | {1} | {2} | {1} |
| 第3号に関するもの a 電気機器及び電気材料 |
○電気機器学 ○電気材料 ○パワーエレクトロニクス |
6 | 5 | 5 | 3 |
| b 電力応用 | ○照明 ○電熱 ○電動機応用 ○電気化学変換 ○電気光変換 ○電気加工(放電応用を含む) ○自動制御または制御工学 ○メカトロニクス |
4 | 3 | 3 | 2 |
| c 電気応用実験、電気実習 | ○電気応用実験 ○電気実習 | [3] | [2] | [4] | [4] |
| d 電気機器設計、製図 | ○電気機器設計 ○自動設計製図(CAD) ○電子回路設計 ○電子製図 |
{1} | {1} | {2} | {1} |
| 第4号に関するもの 電気法規・電気施設管理 |
◎電気法規 ◎電気施設管理 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| [電気実験、電気実習]合計 | [6] | [5] | [11] | [10] | |
| {電気機器設計、製図}合計 | {2} | {2} | {4} | {2} | |
| 総合計 | 43 | 33 | 40 | 26 |
- [電気実験、電気実習]合計、{電気機器設計、製図}合計において、必要取得単位数を満たしていれば各区分ごとに分けなくてもよい。
- 「電気実験、電気実習」、「電気機器設計、電気製図」はそれぞれ区分2又は区分3の任意区分へ繰り入れてもよい。
- 高等学校等において、昭和41年7月9日以前に卒業した者は、[電気実験、電気実習]に関する科目の必要単位数は、8単位でよいものとする。
- 昭和43年3月末までに認定校を卒業した者は、「電気法規及び電気施設管理」の学科目については、履修しなくてもよいものとする。
- 高等学校等において、高等学校学習指導要領(昭和45年10月15日)に規定された「電気工学I」、「電気工学II」及び「電気工学III」の科目により授業を受けたときは、電気工学I:6単位以上、電気工学II:7単位以上、電気工学III:4単位以上 をもって表の区分1a、2a、3a、b及び4に該当するものとみなす。
なお、「電気工学II」の全部又は一部にかえて「電気機器」、「発送配電」及び「電気応用」の科目の授業を行った場合は、これらの単位数の合計が上記の単位数を満足しなければならない。 - 高等学校等において、高等学校学習指導要領(昭和53年8月30日)に規定された「電気基礎」、「電気技術I」及び「電気技術II」の科目により授業を受けたときは、電気基礎:7単位以上、電気技術I:6単位以上、電気技術II:4単位以上をもって表の区分1a、2a、3a、b及び4に該当するものとみなす。
- 高等学校等において、高等学校学習指導要領(平成元年3月15日)に規定された「電気基礎」、「電子技術」、「電力技術」、「電気機器」及び「電力応用」の科目により授業を受けたときは、電気基礎:7単位以上、電力技術:3単位以上、電気機器:3単位以上、電子技術:2単位以上、電力応用:2単位以上をもって表の区分1a、2a、3a、b及び4に該当するものとみなす。また、「工業基礎(3単位)」または「課題研究(2単位以上)」の科目の内容が電気実験及び電気実習に密接に関連する内容のものであれば、「電気実験及び電気実習」の単位数をそれぞれ2単位を限度として減ずることができるものとする。
- 高等学校等において、表の区分1a、2a、3a、b及び4の科目のうち1科目又は2科目について必要単位数より各1単位多く取得している場合、[電気実験、電気実習]の必要単位数をそれぞれ1単位又は2単位減ずることができるものとする。
- 表の区分2aと4は合算した単位数がそれぞれ大学等:8単位以上、短大、高専等:6単位以上、高校等:3単位以上を満足すればよいものとする。
| 科目区分 | 授業科目 | 大学等 | 短大等 | 高専等 | 高校等 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1号に関するもの a 電気・電子工学等の基礎 |
◎電気磁気学 ◎電気回路理論 ○電子回路理論 ○電子工学 ◎電気計測または電子計測 ○システム基礎論 ○電気電子物性 |
17 | 12 | 12 | 6 |
| b 電気基礎実験 | ◎電気基礎実験 ○電子実験 | [2] | [2] | [3] | [4] |
| 第2号に関するもの a 発電、変電、送電、 配電、電気材料等 |
◎発電工学・発電用原動機に関するもの ◎変電工学 ◎送電工学 ◎配電工学 ◎電気材料 ○高電圧工学 ○システム工学 ○エネルギー変換工学 |
7 | 5 | 5 | 2 |
| b 電気応用実験、電気実習 | 電気応用実験 ○電気実習 ○電子実習 |
[1] | [1] | [2] | [2] |
| c 電気製図 | ○電気製図 | {1} | {1} | {1} | {1} |
| 第3号に関するもの a 電気・電子機器、自動制御、 電気エネルギーの利用、 情報伝送・処理等 |
◎電気機器学 ◎パワーエレクトロニクス ◎自動制御または制御工学 ○電動機応用 ○照明 ○電気加工(放電応用を含む) ○電熱 ○メカトロニクス ○電気化学変換 ○電気光変換 ○情報伝送・処理 ○電子計算機 |
10 | 8 | 8 | 5 |
| b 電気応用実験、電気実習 | ○電気応用実験 ○電気実習 | [3] | [2] | [3] | [4] |
| c 電気・電子機器設計、製図 | ○電気機器設計 ○自動設計製図(CAD) ○電子回路設計 ○電子製図 |
{1} | {1} | {1} | {1} |
| 第4号に関するもの 電気法規・電気施設管理 |
◎電気法規・電気施設管理 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| [電気実験、電気実習]合計 | [6] | [5] | [8] | [10] | |
| {電気電子機器設計、製図}合計 | {2} | {2} | {2} | {2} | |
| 総合計 | 43 | 33 | 36 | 26 |
- 「電気応用実験、電気実習」、「電気製図」はそれぞれ区分2又は区分3の任意区分へ繰り入れてもよい。
- 次のいずれかに該当する者にあっては、「電気材料」は、必ずしも履修しなくてもよい。
(1)平成22年4月以降に入学した者
(2)大学、短期大学若しくは高等専門学校又はこれらと同等以上の教育施設を卒業した者であって、「高電圧工学」を履修した者
(3)高等学校又はこれと同等以上の教育施設を卒業した者であって、「電気機器学」(電気材料の内容が含まれている場合に限る。)を履修した者 - 「電動機応用」、「照明」、「電熱」、「電気化学変換」又は「電気加工(放電応用を含む。)」 の内容の一部を含んでいれば、「電気応用」でもよい。
- 高等専門学校等にあっては、「電気実験、電気実習」及び「電気・電子機器設計、製図」のそれぞれの合計単位数で基準単位数を超える単位数がある場合には、基準単位数を超えた単位数の2分の1の単位数を区分1a、2a及び3aにそれぞれ1単位を限度として振り替えることができる。
- 高等学校等において、高等学校学習指導要領(平成元年3月15日)に規定された学科目により授業を受けたときは、次の学科目及び単位をもって表の区分毎の単位に該当するものとする。
- 区分1aに関するものは、(1)から(3)のいずれかの学科目及び単位とする。
(1)電気基礎:6単位以上
(2)電子基礎:6単位以上
(3)電気基礎又は電子基礎:4単位以上+電子技術又は電子回路:2単位以上 - 区分2a及び区分4に関するものは、次の学科目及び単位とする。
電力技術:3単位以上 - 区分3aに関するものは、(4)・(5)のいずれかの学科目及び単位とする。
(4)電気機器:2単位以上+電力応用:2単位以上+情報技術基礎又は電子情報技術:1単位以上(計5単位以上)
(5)電気機器:2単位以上+電子計測制御:2単位以上+情報技術基礎又は電子情報技術:1単位以上(計5単位以上) - 実験・実習に関するものは、工業基礎:3単位以上、課題研究:2単位以上をもってそれぞれ2単位とみなすことができる。
(ただし、工業基礎及び課題研究は、電気実験及び電気実習に密接に関係していること。) - 電気・電子機器設計及び製図に関するものは、(6)電気製図:2単位以上または(7)電子製図:2単位以上とする。
- 区分1aに関するものは、(1)から(3)のいずれかの学科目及び単位とする。
- 「高等学校又はこれと同等以上の教育施設」の種類において、高等学校学習指導要領(平成11年文部省告示第58号)に規定された科目により授業を行うときは、次の科目及び単位数をもって表の科目区分ごとの単位数に該当するものとする。
- 「電気工学又は電子工学等の基礎に関するもの」は、次のいずれかの科目及び単位数とする。
(1)電気基礎:6単位以上
(2)電気基礎:4単位以上+電子技術又は電子回路:2単位以上(計6単位以上)
(3)生産システム技術:4単位以上+電子技術又は電子回路:2単位以上(計6単位以上)
ただし、生産システム技術については、別表第2「電気工学又は電子工学等の基礎に関するもの」の授業内容の科目であること。 - 「発電、変電、送電、配電及び電気材料並びに電気法規に関するもの」は、次の科目及び単位数とする。
電力技術:3単位以上
ただし、別表第2「発電、変電、送電、配電及び電気材料並びに電気法規に関するもの」の授業内容の科目であること。 - 「電気及び電子機器、自動制御、電気エネルギーの利用並びに情報伝送及び処理に関するもの」は、次のいずれかの科目及び単位数とする。ここで、情報技術基礎に代えて電子情報技術にしてもよい。
(1)電気機器:2単位以上+電力技術:2単位以上+情報技術基礎又は電子情報技術:1単位以上(計5単位以上)
ただし、電力技術については、別表第2「電気及び電子機器、自動制御、電気エネルギー利用並びに情報伝送及び処理に関するもの」の授業内容の科目であること。
(2)電気機器:2単位以上+電子計測制御:2単位以上+情報技術基礎又は電子情報技術:1単位以上(計5単位以上) - 「電気工学若しくは電子工学実験又は電気工学若しくは電子工学実習に関するもの」は、次の科目及び単位数とする。
電気実習又は電子実習:10単位以上
ただし、同要領に規定された「工業技術基礎(3単位以上)」又は「課題研究(2単位以上)」の科目の授業を行う場合は、これらの内容が電気工学実験及び電気工学実習に密接に関連する内容のものであれば、「電気工学若しくは電子工学実験又は電気工学若しくは電子工学実習に関するもの」の単位数をそれぞれ2単位を限度として減ずることができるものとする。 - 「電気及び電子機器設計又は電気及び電子機器製図に関するもの」は、次のいずれかの科目及び単位数とする。
(1)電気製図:2単位以上
(2)電子製図:2単位以上
- 「電気工学又は電子工学等の基礎に関するもの」は、次のいずれかの科目及び単位数とする。
- 「高等学校又はこれと同等以上の教育施設」の種類において、高等学校学習指導要領(平成30年文部科学省告示第68号)に規定された科目により授業を行うときは、次の科目及び単位数をもって表の科目区分ごとの単位数に該当するものとする。
- 「電気工学又は電子工学等の基礎に関するもの」は、次のいずれかの科目及び単位数とする。
(1)電気回路:6単位以上
(2)電気回路:4単位以上+電子技術又は電子回路:2単位以上(計6単位以上)
(3)生産技術:4単位以上+電子技術又は電子回路:2単位以上(計6単位以上)
ただし、生産技術については、別表第2「電気工学又は電子工学等の基礎に関するもの」の授業内容の科目であること。 - 「発電、変電、送電、配電及び電気材料並びに電気法規に関するもの」は、次の科目及び単位とする。
電力技術:3単位以上
ただし、別表第2「発電、変電、送電、配電及び電気材料並びに電気法規に関するもの」の授業内容の科目であること。 - 「電気及び電子機器、自動制御、電気エネルギーの利用並びに情報伝送及び処理に関するもの」は、次のいずれかの科目及び単位数とする。ここで、工業情報数理に代えてハードウェア技術にしてもよい。
(1)電気機器:2単位以上+電力技術:2単位以上+工業情報数理又はハードウェア技術:1単位以上(計5単位以上)
ただし、電力技術については、別表第2「自動制御、電気エネルギー利用並びに情報伝送及び処理に関するもの」の授業内容の科目であること。
(2)電気機器:2単位以上+電子計測制御:2単位以上+工業情報数理又はハードウェア技術:1単位以上(計5単位以上) - 「電気工学若しくは電子工学実験又は電気工学若しくは電子工学実習に関するもの」は、次の科目及び単位数とする。
電気実習又は電子実習:10単位以上
ただし、同要領に規定された「工業技術基礎(3単位以上)」又は「課題研究(2単位以上)」の科目の授業を行う場合は、これらの内容が電気工学実験及び電気工学実習に密接に関連する内容のものであれば、「電気工学若しくは電子工学実験又は電気工学若しくは電子工学実習に関するもの」の単位数をそれぞれ2単位を限度として減ずることができるものとする。 - 「電気及び電子機器設計又は電気及び電子機器製図に関するもの」は、次のいずれかの科目及び単位数とする。
(1)電気製図:2単位以上
(2)電子製図:2単位以上
- 「電気工学又は電子工学等の基礎に関するもの」は、次のいずれかの科目及び単位数とする。
- 表の区分2aと4は合算した単位数がそれぞれ大学等:8単位以上、短大、高専等:6単位以上、高校など:3単位以上を満足すればよいものとする。
このページのお問合せ先
| 住所 | 〒980-0014 仙台市青葉区本町3-2-23 仙台第2合同庁舎8階 |
|---|---|
| 電話 | 022-221-4951 |
| FAX(共通) | 022-224-4370 |
最終更新日:2024年5月10日