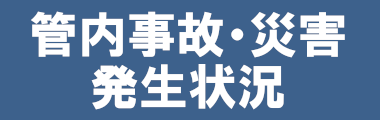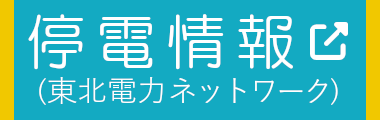作業の区分
作業監督者の選任には作業区分毎に資格が必要です。 現在の鉱山保安法では、独自の国家試験制度はなく、電気事業法、高圧ガス保安法等他法律の資格要件を規定しています。
- 火薬類の存置、受渡し、運搬及び発破(石油鉱山(石油坑によるものを除く。)においては、火薬類の使用)に関する作業
- ボイラー(小型ボイラーを除く。)又は蒸気圧力容器に関する作業
- 一日に容積百立方メートル以上の高圧ガス(内燃機関の始動、タイヤの空気の充てん又は削岩の用に供する圧縮装置内における圧縮空気を除く。)を製造するための設備(冷凍設備及び昇圧供給装置を除く。)に関する作業
- 冷凍設備(冷凍のためガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備でその一日の冷凍能力が二十トン未満(フルオロカーボン(不活性のものに限る。)にあっては五十トン未満)のもの、冷凍保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十一号)第三十六条第二項に掲げる施設(同項第一号の製造施設にあってはアンモニアを冷媒ガスとするものに限る。)であって、その製造設備の一日の冷凍能力が五十トン未満のものを除く。)に関する作業
- 昇圧供給装置に関する作業(天然ガス自動車への天然ガスの充てん作業を除く。)
- 電気工作物(電圧三十ボルト未満のものを除く。ただし、石炭坑及び石油坑において使用する電圧三十ボルト未満の電気的設備であって、電圧三十ボルト以上の電気的設備と電気的に接続されていないものはこの限りでない。以下同じ。)の工事、維持及び運用に関する作業
- ガス集合溶接装置に関する作業
- 石油鉱山において行うパイプライン及びその附属設備に関する作業
- 鉱煙発生施設の鉱害防止に関する作業
- 坑廃水処理施設の鉱害防止に関する作業
- 騒音発生施設(公害防止組織法施行令第四条に掲げる施設(騒音指定地域内にあるものに限る。)に限る。)の鉱害防止に関する作業
- 振動発生施設(公害防止組織法施行令第五条の二に掲げる施設(振動指定地域内にあるものに限る。)に限る。)の鉱害防止に関する作業
- ダイオキシン類発生施設(公害防止組織法施行令第五条の三第一項に掲げる施設に限る。)の鉱害防止に関する作業
- 粉じん発生施設の鉱害防止に関する作業
- 石綿粉じん発生施設の鉱害防止に関する作業
- 鉱業廃棄物の処理施設の鉱害防止に関する作業
- 有害鉱業廃棄物の処理施設の鉱害防止に関する作業
一 火薬類の存置、受渡し、運搬及び発破(石油鉱山(石油坑によるものを除く。)においては、火薬類の使用)に関する作業
作業監督者の資格
火薬類取締法に基づく火薬類取扱保安責任者免状を有する者のうちから選任する必要があります。(作業によって必要となる資格の種類が異なります。)「火薬類取扱保安責任者免状」の取得方法
火薬類取扱保安責任者試験を受験して資格を取得する必要があります。
公益社団法人 全国火薬類保安協会![]() 電話:03-3553-8762
電話:03-3553-8762
- 学歴、年齢及び実務経験等の制限:特になし
- 年1回実施
受験講習会等
国家試験を受験する者に向けた受験講習会を各都道府県火薬類保安協会が開催しています。
学歴、年齢及び実務経験等の制限:なし
- 秋田県火薬類保安協会 電話:090-6685-8648
- (一社)岩手県火薬類保安協会
 電話:019-651-9826
電話:019-651-9826 - (一社)宮城県火薬類保安協会
 電話:022-225-0931
電話:022-225-0931 - 山形県危険物安全協会連合会
 電話:023-632-5744
電話:023-632-5744 - (一社)福島県火薬類保安協会
 電話:024-944-3169
電話:024-944-3169
二 ボイラー(小型ボイラーを除く。)または蒸気圧力容器に関する作業
作業監督者の資格
ボイラー及び圧力容器安全規則に基づく特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許若しくは二級ボイラー技士免許を受けた者又は化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習若しくは普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習を修了した者のうちから選任する必要があります。(作業によって必要となる資格の種類が異なります。)
「ボイラー技士免許」の取得方法
ボイラー技士免許試験を受験して資格を取得する必要があります。
公益財団法人 安全衛生技術試験協会![]() 電話:03-5275-1088
電話:03-5275-1088
東北安全衛生技術センター![]() 電話:0223-23-3181
電話:0223-23-3181
- 学歴、年齢及び実務経験等の制限:特級、一級ともに技術資格又は学歴に応じた実務経験が必要
- 特級:年1回実施、一級:概ね2ヶ月に1回実施、二級:概ね1ヶ月に1回実施
- 全国6箇所の安全衛生技術センターの他、センターの所在地外で出張試験有り
第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習
一般社団法人 日本ボイラ協会![]() 電話:03-5473-4500
電話:03-5473-4500
宮城支部 電話:022-224-2245
福島支部 電話:024-522-6718
- 学歴、年齢及び実務経験等の制限:「普通」は特になし、「化学設備関係」は化学設備の取扱い作業に5年以上従事した経験が必要
- 受講時間:「普通」12時間、「化学設備関係」21時間
- 支部毎に概ね年1回開催(「化学設備関係」は未開催の支部あり)
実技講習・受験講習会等
- ボイラー取扱いの実務経験を有しない者が二級ボイラー技士免許試験に合格した場合は、厚生労働省の都道府県労働局に登録した講習機関が定期的に開催している「ボイラー実技講習」(20時間)を修了することにより免許をうけることができます。
登録教習機関については、都道府県労働局のホームページ 等をご参照ください。
等をご参照ください。 - 国家試験を受験する者に向けた受験講習会を日本ボイラ協会が開催しています。
三 一日に容積百立方メートル以上の高圧ガス(内燃機関の始動、タイヤの空気の充てん又は削岩の用に供する圧縮装置内における圧縮空気を除く。)を製造するための設備(冷凍設備及び昇圧供給装置を除く。)に関する作業
作業監督者の資格
高圧ガス保安法に基づく化学責任者免状又は機械責任者免状を有する者のうちから選任する必要があります。
「化学責任者免状」「機械責任者免状」の取得方法
高圧ガス製造保安責任者試験を受験して資格を取得する必要があります。
高圧ガス保安協会![]() 電話:03-3436-6106(試験センター)
電話:03-3436-6106(試験センター)
東北支部 電話:022-268-7501
- 学歴、年齢及び実務経験等の制限:特になし
- 年1回実施
高圧ガス製造保安責任者講習(冷凍以外)
高圧ガス保安協会が行う講習の課程を修了した者は試験の一部について免除を申請することができます。
高圧ガス保安協会教育事業部![]() 電話:03-3436-6102
電話:03-3436-6102
- 学歴、年齢及び実務経験等の制限:特になし
- 受講時間:21時間
- 甲種化学・甲種機械:年1回開催、乙種化学・乙種機械・丙種(液石・特別):年2回開催
四 冷凍設備(冷凍のためガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備でその一日の冷凍能力が二十トン未満(フルオロカーボン(不活性のものに限る。)にあっては五十トン未満)のもの、冷凍保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十一号)第三十六条第二項に掲げる施設(同項第一号の製造施設にあってはアンモニアを冷媒ガスとするものに限る。)であって、その製造設備の一日の冷凍能力が五十トン未満のものを除く。)に関する作業
作業監督者の資格
高圧ガス保安法に基づく冷凍機械責任者免状を有する者のうちから選任する必要があります。(作業によって必要となる資格の種類が異なります。)
「冷凍機械責任者免状」の取得方法
高圧ガス製造保安責任者試験を受験して資格を取得する必要があります。
高圧ガス保安協会![]() 電話:03-3436-6106(試験センター)
電話:03-3436-6106(試験センター)
東北支部 電話:022-268-7501
- 学歴、年齢及び実務経験等の制限:特になし
- 年1回実施
高圧ガス製造保安責任者講習(冷凍)
高圧ガス保安協会が行う講習の課程を修了した者は試験の一部について免除を申請することができます。
高圧ガス保安協会教育事業部![]() 電話:03-3436-6102
電話:03-3436-6102
- 学歴、年齢及び実務経験等の制限:特になし
- 受講時間:21時間
- 第一種:年1回開催、第二種・第三種:年2回開催
五 昇圧供給装置に関する作業(天然ガス自動車への天然ガスの充てん作業を除く。)
作業監督者の資格
上記の高圧ガス保安法に基づく化学責任者免状又は機械責任者免状を有する者、又はガス事業法に基づくガス主任技術者免状を有する者のうちから選任する必要があります。(作業によって必要となる資格の種類が異なります。)
「ガス主任技術者免状」の取得方法
ガス主任技術者試験を受験して資格を取得する必要があります。
一般財団法人 日本ガス機器検査協会![]() 電話:03-3960-0159(ガス主任技術者試験センター)
電話:03-3960-0159(ガス主任技術者試験センター)
- 学歴、年齢及び実務経験等の制限:特になし
- 年1回実施
六 電気工作物(電圧三十ボルト未満のものを除く。ただし、石炭坑及び石油坑において使用する電圧三十ボルト未満の電気的設備であって、電圧三十ボルト以上の電気的設備と電気的に接続されていないものはこの限りでない。以下同じ。)の工事、維持及び運用に関する作業
作業監督者の資格
1、2、3から選任する必要があります。(作業によって必要となる資格の種類が異なります。)
- 電気事業法に基づく電気主任技術者免状を有する者
- 同法第43条第2項に規定する許可の要件を満たす者であって産業保安監督部長が認めた者
- 同法施行規則第52条第2項の承認を受ける要件を満たす者のうち産業保安監督部長が認めた者であって委託契約の相手方
「電気主任技術者免状」の取得方法
電気主任技術者試験を受験して資格を取得する方法と、学歴又は資格及び実務の経験のある者が書類審査を経て有資格者となる方法があります。
電気主任技術者試験(毎年1回実施)
一般財団法人 電気技術者試験センター![]() 電話:03-3552-7651
電話:03-3552-7651
学歴、年齢及び実務経験等の制限:特になし
学歴又は資格及び実務の経験により取得する場合
事務局:各地方産業保安監督部の電力安全課
東北:関東東北産業保安監督部東北支部 電力安全課 電話:022-221-4951(電気業務係)
電気事業法第43条第2項の許可の要件を満たす者、同法施行規則第52条第2項の承認を受ける要件を満たす者の運用通達
電気設備の申請・届出等の手引き内「主任技術者制度の解釈及び運用」![]() 参照
参照
七 ガス集合溶接装置に関する作業
作業監督者の資格
労働安全衛生法に基づくガス溶接作業主任者免許を受けた者のうちから選任する必要があります。
「溶接作業主任者免許」の取得方法
免許を受けることができる者は、「ガス溶接作業主任者免許試験に合格した者」、「職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校が行う同法第二十七条第一項の指導員訓練のうち職業能力開発促進法施行規則別表第九の訓練科の欄に掲げる塑性加工科又は溶接科の訓練を修了した者」、「その他厚生労働大臣が定める者」です。
ガス溶接作業主任者免許試験(毎年2回実施)
公益財団法人 安全衛生技術試験協会![]() 電話:03-5275-1088
電話:03-5275-1088
東北安全衛生技術センター![]() 電話:0223-23-3181
電話:0223-23-3181
学歴、年齢及び実務経験等の制限:技術資格又は学歴に応じた実務経験が必要
講習会等
- ガス溶接作業主任者免許試験を受験するには技術資格又は学歴に応じた実務経験が必要であり、代表的な技術資格に厚生労働省の都道府県労働局に登録した教習機関が実施している「ガス溶接技能講習」の修了があります。ただし、この講習を終了し、その後ガス溶接等の業務に3年以上従事した経験が必要です。
登録教習機関については、都道府県労働局のホームページ 等をご参照ください。
等をご参照ください。 - ガス溶接作業主任者免許試験を受験する者に向けた受験講習会を一部の都道府県労働基準協会が開催しています。
八 石油鉱山において行うパイプライン及びその附属設備に関する作業
作業監督者の資格
上記のガス事業法に基づくガス主任技術者免状を有する者、高圧ガス保安法に基づく化学責任者免状又は機械責任者免状を有する者、消防法に基づく甲種又は乙種危険物取扱者免状(第4類)を有する者のうちから選任する必要があります。(作業によって必要となる資格の種類が異なります。)
「危険物取扱者免状」の取得方法
危険物取扱者試験を受験して資格を取得する必要があります。
一般財団法人 消防試験研究センター![]() 電話:03-3597-0220(本部)
電話:03-3597-0220(本部)
- 青森県支部 電話:017-722-1902
- 岩手県支部 電話:019-654-7006
- 宮城県支部 電話:022-276-4840
- 秋田県支部 電話:018-836-5673
- 山形県支部 電話:023-631-0761
- 福島県支部 電話:024-524-1474
学歴、年齢及び実務経験等の制限
甲種:一定の資格が必要- 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学又は高等専門学校において化学に関する学科又は課程を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして総務省令で定める者
- 乙種危険物取扱者免状の交付を受けた後二年以上危険物取扱の実務経験を有する者 等
受験講習会等
国家試験を受験する者に向けた受験講習会を各都道府県及び各地区の危険物安全協会が開催しています。
一般財団法人 全国危険物安全協会![]() 電話:03-5962-8921
電話:03-5962-8921
- 青森県危険物安全協会連合会 電話:017-722-1400
- (一社)岩手県危険物安全協会連合会
 電話:019-654-3991
電話:019-654-3991 - (一社)宮城県危険物安全協会連合会
 電話:022-276-4850
電話:022-276-4850 - (一社)秋田県危険物安全協会連合会
 電話:018-867-2245
電話:018-867-2245 - 山形県危険物安全協会連合会
 電話:023-632-5744
電話:023-632-5744 - (一社)福島県危険物安全協会連合会
 電話:024-573-9600
電話:024-573-9600
九 鉱煙発生施設の鉱害防止に関する作業
十 坑廃水処理施設の鉱害防止に関する作業
十一 騒音発生施設(公害防止組織法施行令第四条に掲げる施設(騒音指定地域内にあるものに限る。)に限る。)の鉱害防止に関する作業
十二 振動発生施設(公害防止組織法施行令第五条の二に掲げる施設(振動指定地域内にあるものに限る。)に限る。)の鉱害防止に関する作業
十三 ダイオキシン類発生施設(公害防止組織法施行令第五条の三第一項に掲げる施設に限る。)の鉱害防止に関する作業
十四 粉じん発生施設の鉱害防止に関する作業
十五 石綿粉じん発生施設の鉱害防止に関する作業
作業監督者の資格
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく公害防止管理者になる資格を有する者のうちから選任する必要があります。
(作業によって必要となる資格の種類が異なります。)
「公害防止管理者」の取得方法
公害防止管理者試験を受験して資格を取得する方法と、技術資格又は学歴及び実務経験のある者が書類審査を経て一定の講習を受講し、有資格者となる方法があります。
公害防止管理者試験(毎年1回実施)
一般社団法人 産業環境管理協会![]() 電話:03-3528-8156(公害防止管理者試験センター)
電話:03-3528-8156(公害防止管理者試験センター)
東北支部(分室) 電話:022-225-1565
学歴、年齢及び実務経験等の制限:特になし
認定講習
公害防止管理者試験センター![]() 【全ての講習区分について実施】電話:03-3528-8156
【全ての講習区分について実施】電話:03-3528-8156
一般社団法人 日本砕石協会![]() 【「一般粉じん関係」について実施】電話:03-5435-8830(本部)
【「一般粉じん関係」について実施】電話:03-5435-8830(本部)
受講条件:技術資格又は学歴及び実務経験資格が必要
※注:大気関係第1種、水質関係第1種は学歴及び実務経験資格での受講は不可
十六 鉱業廃棄物の処理施設の鉱害防止に関する作業
作業監督者の資格
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第17条に掲げる資格(技術士法に基づく技術士(条件あり)又は下欄の「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の17第2号イからチ」の学歴・実務経験を有する者等)を有する者のうちから選任する必要があります。「技術士」の取得方法
技術士試験を受験して資格を取得する必要があります。
第一次試験(筆記)及び第二次試験(筆記及び口頭)があり、技術部門毎に実施されます。
公益社団法人 日本技術士会![]() 電話:03-6432-4585(技術士試験センター)
電話:03-6432-4585(技術士試験センター)
- 第一次試験(年1回実施)
- 学歴、年齢及び実務経験等の制限:特になし
- 第二次試験(年1回実施)
- 学歴、年齢及び実務経験等の制限:次の2つの要件を満たしていること。
-
- 第一次試験に合格又は指定された教育課程を修了
- 科学技術に関する業務について、条件により4年超又は7年超の実務経験が必要
講習会等
技術管理者となる者の資格要件を補完する講習として、一般財団法人 日本環境衛生センターが廃棄物処理施設技術管理者講習(基礎・管理課程)を実施しています。
一般財団法人 日本環境衛生センター![]() 電話:044-288-4919(東日本支局 サステナブル社会推進部)
電話:044-288-4919(東日本支局 サステナブル社会推進部)
学歴、年齢及び実務経験等の制限:年齢18歳以上
十七 有害鉱業廃棄物の処理施設の鉱害防止に関する作業
作業監督者の資格
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の17第2号」に掲げる資格を有する者のうちから選任する必要があります。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の17第2号(抜粋)
- 二年以上法第二十条に規定する環境衛生指導員の職にあつた者
- 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。ハにおいて同じ。)又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあつては、土木工学。ハにおいて同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、二年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
- 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、三年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
- 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあつては、土木工学。ホにおいて同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、四年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
- 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、五年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
- 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号 )に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、六年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
- 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、七年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
- 十年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
- イからチまでに掲げる者と同等以上の知識を有すると認められる者
講習会等
公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターが実施する特別管理産業廃棄物管理責任者講習会修了者は、都道府県等において「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の17第2号リ」に掲げる「同等以上の知識を有すると認められる者」として認定されています。
特別管理産業廃棄物管理責任者講習会は各都道府県協会が窓口となっています。 受講資格は特にありません。
公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター![]() 電話:03-5807-5913(教育研修部)
電話:03-5807-5913(教育研修部)
- (一社)青森県産業資源循環協会
 電話:017-721-3911
電話:017-721-3911 - (一社)岩手県産業資源循環協会
 電話:019-625-2201
電話:019-625-2201 - (一社)宮城県産業資源循環協会
 電話:022-290-3810
電話:022-290-3810 - (一社)秋田県産業資源循環協会
 電話:018-863-7107
電話:018-863-7107 - (一社)山形県産業資源循環協会
 電話:023-624-5560
電話:023-624-5560 - (一社)福島県産業資源循環協会
 電話:024-524-1953
電話:024-524-1953
注意事項
- 講習会について記載のある欄は、現在把握しているものを参考として掲載したものです。 このため、他に講習会を実施している機関がある場合には把握次第随時追加します。
ただし、多数の機関で受験講習会を実施している資格については掲載しておりません。 - 掲載した団体の講習会を推奨するものではありません。
- 上記資格の他、旧保安技術職員国家試験規則の合格者も、作業の区分に応じて作業監督者の資格があります。
- 最新の情報は各団体のホームページ等でご確認ください。
最終更新日:2024年3月27日