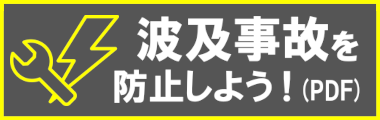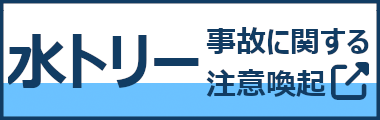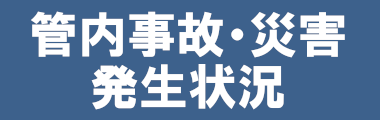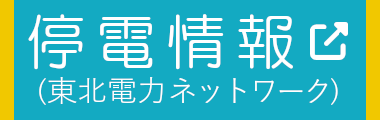電気事業法施行規則別表第2の上欄の発電所の「設置の工事」とは、どのようなものをいうのか。
発電所の「設置の工事」とは、発電所の新設をいい、発電所の移設又は旧設備を廃止して、新しい発電所として再発足する場合も含まれます。
(内燃力を原動力とするものについては、出力10,000kW以上のもの。)
電気事業法施行規則別表第2の「発電所設置の工事」と「発電所変更の工事」のうち「発電設備の設置」とはどのように異なるのか。
「発電所設置の工事」とは、いわゆる発電所を新設する工事のことです。
発電設備とは、発電機ならびにそれと一体となって発電に供される原動力設備、電気設備の総合体をいいます。
つまりユニットを意味するものであり、「発電設備の設置」とは、ユニットの増設あるいは撤去、新設をいいます。
従って、第1号機を建設する場合は、「発電所の設置」の工事であり、第2号機以降を増設する場合は、「発電設備の設置」の工事となります。
電気事業法施行規則別表第2の「取替え」とは、どのようなものをいうのか。
「取替え」とは、設備又は機器を従前のものとそっくり同一使用・同一材料のものと取り替える工事をいいます。
なお、発電機のみの取り替え(同一使用、同一材料)については、工事計画届出等の手続は不要です。
工事計画における工事開始はいつの時点をいうのか。また、取替え、改造・修理等の工事計画はいつの時点が着工となるのか。
工事計画における工事開始とは、本体装置との一体性・工事の連続性を考え、基礎杭を打つ場合は「基礎杭打ちが行われる日」、基礎杭を打たない場合は「基礎コンクリートの打設工事が行われる日」となります。
なお、用地の取得や整地作業、道路工事、仮設備の設置等準備段階のものは工事開始とみなされません。
基礎コンクリートの打設工事も行わない場合、あるいは部品の取替え、改造・修理等の場合は、「当該作業を開始した日」となります。
電気事業法では、例えば、「工事の開始の日の30日前までに」のように期間を規定したものがあるが、この期間はどのように計算されるのか。
工事の開始の日の30日前(法第48条工事計画届出時期)とは、届出があった日と工事開始の日の間が30日あることを要するものです。
なお、届出があった日とは、工事計画届出書が受理(受付)された日であり、届出書に記載された提出日ではありませんのでご注意ください。
発電所の設置の場合、主任技術者の選任及び選任届出はいつまでに行う必要があるか。
電気事業法第43条第4項の規定に基づき、主任技術者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安監督の職務を行う必要があることから、発電所の設置の場合、その工事着手(基礎工事着手等)までに選任する必要があります。
主任技術者の選任年月日は、社内辞令を受けた日としている場合が一般的であり、電気主任技術者を選任したときは、遅滞なく主任技術者選任届出書を提出する必要があります。
工事計画届出の様式において、タイトルが「工事計画(変更)届出書」となっているが、既設設備を変更する工事を行う場合には、この「(変更)」を付した届出書を提出するのか。
この場合の「(変更)」とは、届け出た工事計画について、使用開始する前に工事計画を変更しようとする場合を意味します。
届出を行う場合は、「工事計画変更届出書」と括弧を外してご記載ください。
なお、既設設備の変更を行う場合のタイトルは工事計画届出書となります。
工事計画変更届出は工事を伴うものだけが対象となるのか。工事中に仕様を変更した場合であって工事を伴わないものはどうなるのか。
(例:内燃機関の燃料の燃焼能力の変更、煙突の口径、地表上の高さの変更等であって、その工事に取りかかる前に設計変更した場合等)
電気事業法第48条では、工事計画届出は工事をしようとするときに届け出るものですが、工事計画変更届出は工事の計画の変更をしようとするときに届け出ることとされています。
従って、変更に係る工事を伴わなくても使用開始前に同法施行規則別表第2、第4に該当する変更を行うのであれば、工事計画変更届出の対象となりますのでご注意ください。
大気汚染防止法のばい煙発生施設に該当する電気工作物とは、どのようなものをいうのか。
大気汚染防止法第2条第2項及び同法施行令第2条において、ばい煙発生施設が定められており、主な電気工作物については以下のとおりとなっています。
なお、大気汚染防止法に規定するディーゼル機関、ガス機関、ガソリン機関は、電気事業法において内燃機関として取り扱われています。
| 主な電気工作物 | 要件 | |
|---|---|---|
| 1 | ボイラー(熱風ボイラーを含み、熱源として電気又は廃熱のみを使用するものを除く。) | 伝熱面積が10平方メートル以上又はバーナーの燃料燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上 |
| 29 | ガスタービン | 燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上 |
| 30 | ディーゼル機関 | |
| 31 | ガス機関 | 燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり35リットル以上 |
| 32 | ガソリン機関 |
工事計画届出を行った内燃機関について、工事中にばい煙量、ばい煙濃度を変更しようとする場合、どのような手続が必要か。
工事中であっても使用方法変更届出が必要になります。
なお、工事計画変更届出が必要となる場合もありますので、事前にご相談願います。
環境に与える影響を低減するために、使用燃料の低硫黄化、煙突の嵩上げを行う場合、工事計画等の手続は必要か。
ばい煙量、ばい煙濃度を変更する場合は、減少する場合でも使用方法変更届出が必要となります。
また、煙突の高さを変更する場合は、工事計画届出が必要となります。
既設発電所において、煙突を建て替える場合、工事計画届出が必要か。
煙突の建て替えは、同一仕様の場合を除いて工事計画届出が必要となります。
また、緊急時用低硫黄重油タンクの設置は、工事計画届出が不要ですが、環境保全の観点から関係資料の提出をお願いする場合もあります。
燃料の低い硫黄化を図り、ばい煙を減少する場合でも電気関係報告規則第4条による届出が必要か。
硫黄分のみに限らず、計画的なばい煙量の変更は全て届出の対象となり、ばい煙量が減少する場合であっても使用方法変更届出が必要となります。
工事計画届出の際に添付する電気事業法施行規則別表第3、別表第5に規定された公害防止関係の説明書とはどのようなものか。様式等が定められているのか。
原子力安全・保安院より発出されている通知文書(平成15年3月31日付け平成15・02・19原院第3号「公害防止関係資料の様式の制定について」)により様式が定められています。
ばい煙関係の届出値とは何か。排出基準等のような遵守義務があるのか。
工事計画届出の際に「ばい煙に関する説明書」に記載したばい煙量・濃度、燃料硫黄分等の値を「届出値」と呼んでいます。
使用方法変更届出等より、これらの値を変更した場合は、届出値も変更となります。
届出値は、ばい煙発生施設の設置者が環境保全のためにばい煙の発生をできるだけ抑制しようと自主的に定めた値であり、排出基準以下となっていなければなりません。
発電設備の運転にあたっては、ばい煙量・濃度が排出基準及び届出値以下となるようにしなければなりません。
また、ばい煙量・濃度を変更しようとする場合には、使用方法変更届出を行う必要があります。
既設の発電設備に排ガスボイラーを設置する場合、手続が必要か。
排ガスの出口温度が低くなることにより煙突の有効高さが小さくなる場合には、あらかじめ使用方法変更届出を行う必要があります。
なお、このような変更は公害対策上はマイナスとなるので、相当K値を増加させないような対策(燃料硫黄分の抑制、煙突の嵩上げ等)を講ずることが望ましいです。
煙突の有効高さの値が小さくなる要因としては、他に、煙突口径の拡大、垂直吹き出しの煙突の横(斜め)吹き出しへの変更、煙突出口への傘、防塵網の取り付け等が考えられ、これらの場合には、工事計画届出又は使用方法変更届出が必要となります。
発電設備の公害防止に関する業務と電気主任技術者との関係について教えてほしい。
ばい煙発生施設の排出基準の適合義務は、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令の第4条に規定されています。
主任技術者は電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督を行うこととされており、また、保安規程には、一般的に電気工作物を技術基準に適合するように維持しなければならないことが定められています。
これらのことから、発電設備の公害防止に関する業務は主任技術者が監督しなければばらないと判断されます。
具体的な監督内容としては、ばい煙測定時期の適否、測定方法の妥当性、測定結果の適否、改善事項の要否の検討、燃料硫黄分の管理、各種手続等が考えられます。
なお、保安管理業務外部委託承認を受けている場合は、外部委託法人、電気管理技術者がこれら業務の監督を行う義務があります(騒音、振動についても同様です)。
ばい煙量等測定報告の必要はなくなったが、ばい煙量等の測定、結果の記録及び記録の保存は今後も必要か。
ばい煙等の測定、結果の記録、記録の保存は大気汚染防止法により義務づけられていることから必要です。
ばい煙に関する説明書の様式 「設置(変更)しようとする発電設備等の概要」 の記載について、「代理人の職・氏名」、「事業場の名称」及び「事業場の所在地」の欄はどのように記載すればよいか。
「代理人の職・氏名」の欄は、原則として代表権を持つ者から委任を受けている者のみでご記入ください。
すなわち、設置者が設置者以外の者(例えば法人の場合は工場長、支店長等)に手続を委任した場合をいいます。ただし、委任の範囲は同一法人となります。
「事業場の名称」及び「事業場の所在地」の欄は、現に設置されている当該電気工作物の設置の場所(工場名等)及び設置場所の所在地をご記入ください。
ばい煙に関する説明書の様式 「設置(変更)しようとする発電設備等の概要」 の記載について、「設置年月」、「着工・使用開始予定年月」の欄は、既設設備の場合、どのように記載すればよいか。
「設置年月」の欄は、既設設備の場合のみ記入し、新設設備の場合は横棒 「-」 としてください。
「着工・使用開始予定年月」の欄は、工事を伴う場合にご記入ください。
使用方法を変更する場合は、変更予定年月をご記入ください。
煙突出口の形状が横向きの場合、煙突の出口に傘を設ける場合等において、煙突の有効高さはどのようになるか。
これらの煙突においては、実高さHoを下図のように扱い、有効高さHeは(Hm+Ht)=0とみなし、He=Hoとして算出しても差し支えありません。
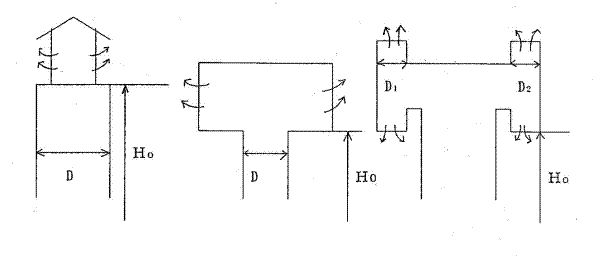
移動用電気工作物は、ばい煙発生施設の規制対象となるか。
基本的には、固定発生源に係るばい煙発生施設が規制の対象となりますが、移動用でも基礎据付の有無にかかわらず同一の場所に長期間設置する場合、対象となり得るケースがありますので、事前にご相談願います。
「非常用予備発電装置」とはいかなるものか。
非常用発電装置は、発電所、変電所、需要設備等の附帯設備として扱われており、非常用の予備電源を得る目的で電気を発生する装置であって、受電又は発電が全停した場合、設備あるいは人身保護のために非常用ポンプ、照明、換気、消火、通信等の用に供する最小保安電力を確保するために設置される発電装置をいいます。
実情としては内燃力設備によるものが一般的です。
また、発電所内外の系統の全停電又は周波数が低下した場合、発電所の所内電源を確保し、系統復旧に合わせて直ちに発電ができるように起動用の電力を得る目的で設置する場合も非常用予備発電装置として扱われます。
内燃力発電所等に設置される主機が事故の場合の対応として、非常用予備発電装置的性格と発電所予備出力的性格を兼ねているものは非常用予備発電装置とは解釈されず、通常の発電装置として扱われます。
非常用予備発電設備を常用の発電設備として使用しようとする場合、どのような手続が必要か。
ばい煙発生施設に該当する場合、以下の手続が必要となります。
(非常用予備発電装置は大気汚染防止法の排出基準の適用が猶予されていますが、常用の発電設備として使用する場合は排出基準が適用されますのでご注意ください。)
- 非常用予備発電装置に係るばい煙発生施設廃止届出書(Word形式:43KB)
(電気関係報告規則第4条第17号) - 発電所(発電設備)の工事を伴う場合:
工事計画届出書(Word形式:66KB)(電気事業法第48条第1項)
発電所(発電設備)の工事を伴わない場合:
ばい煙発生施設設置届出書(Word形式:45KB)(電気係報告規則第4条第1号)
発電所出力変更報告書(Word形式:48KB)(電気関係報告規則第5条) - 保安規程変更届出書(Word形式:39KB)(電気事業法第42条第2項)
- 原動機がガスタービンの場合:
ボイラー・タービン主任技術者選任届出書(Word形式:176KB)(電気事業法第43条第3項)
ばい煙発生施設に該当しない場合は、発電所出力変更報告書、保安規程変更届出書、ボイラー・タービン主任技術者選任届出書(原動機がガスタービンの場合)等が必要となります。
なお、ばい煙発生施設に該当する常用の発電設備を非常用予備発電設備として使用する場合は、常用の発電設備に係るばい煙発生施設廃止届出書、発電所廃止報告書又は発電所出力変更報告書、工事計画届出書(工事を伴う場合)、非常用予備発電装置に係るばい煙発生施設設置届出書(工事を伴わない場合)、保安規程変更届出書等が必要となります。
(ばい煙発生施設に該当しない場合は、発電所廃止報告又は発電所出力変更報告書、保安規程変更届出書が必要となります。)
騒音規制法の特定施設に該当する電気工作物とは、どのようなものをいうのか。
騒音規制法第2条第1項及び同法施行令第1条において特定施設が定められており、主な電気工作物については以下のとおりとなっています。
2 空気圧縮機及び送風機 原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。
振動規制法の特定施設に該当する電気工作物とは、どのようなものをいうのか。
振動規制法第2条第1項及び同法施行令第1条において特定施設が定められており、主な電気工作物については以下のとおりとなっています。
2 圧縮機 原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。
各地域における騒音(振動)規制値はどのように決められているのか。
また、条例との関係はどうなっているのか。
「騒音(振動)に関する説明書」の規制基準の欄には何を記載するのか。
騒音規制法(振動規制法)第3条及び第4条の規定に基づき、都道府県知事は規制する地域を指定するとともに、規制値を定め公示することになっています。
また、条例では、法の範囲を超えない範囲で騒音(振動)の大きさを規制することができます。
「騒音(振動)に関する説明書」の規制基準の欄には、騒音規制法(振動規制法)に基づき公示された値をご記載ください。
騒音規制法第2条において、騒音の規制基準は「敷地の境界線における大きさの許容限度」と定められているが、「敷地の境界線」すべてが基準値以内である必要があるか。住居に最も近い境界線のみでよいのではないか。
「敷地の境界線」すべてとなります。
ただし、海岸線等明らかに生活環境が損なわれるものでないと判断できる場合は除外されています。なお、敷地境界線とは、発電所の境界線をいうのではなく、工場又は事業場の敷地境界線をいいます。
自家用発電所で発電設備の一部を廃止する場合、どのような手続をすればよいのか。
・発電設備の一部を廃止することにより、発電出力に変更があるとき。
・発電設備の一部を廃止したが、発電出力に変更がないとき。
発電所の出力を変更する場合は、電気関係報告規則第5条に基づき、発電所出力変更報告書を提出する必要があります。
(工事計画届出書等を提出している場合は除きます。)
なお、発電所の出力に変更がない場合は、発電所出力変更報告書の提出は不要ですが、ばい煙発生施設(特定施設)に該当するものを廃止した場合、電気関係報告規則第4条第17号の規定に基づき、ばい煙発生施設(特定施設)廃止届出書を提出する必要があります。
ばい煙発生施設(特定施設)がある発電所において、変更届出が必要となるのはどのような場合か。
電気関係報告規則第4条第16号の規定に基づき、設置者が法人にあっては、名称(会社名、事業場名等)、住所(本社、工場、事業場等の住所)、代表者氏名、その他(個人等)にあっては、氏名、住所に変更があった場合、変更届出書の提出が必要となります。
また、ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物を有する発電所においては、設置者の氏名(法人にあってはその名称)・住所、事業場の名称・所在地、当該電気工作物の使用状態(設置又は予備の別)に変更があった場合、変更届出書が必要となります。
(名称、住所、法人代表者氏名)変更届出書(Word形式:46KB)
ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物変更届出書(Word形式:22KB)